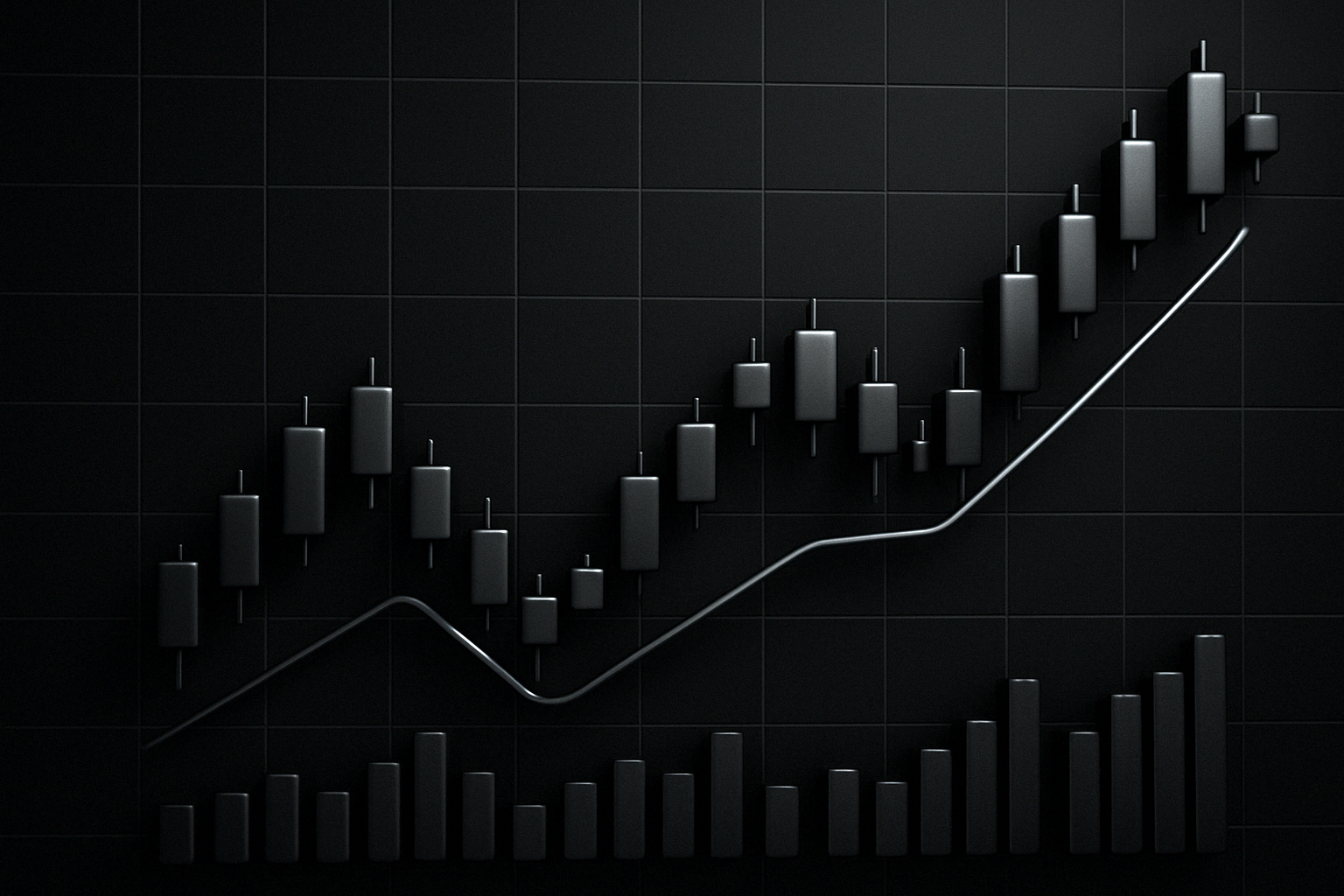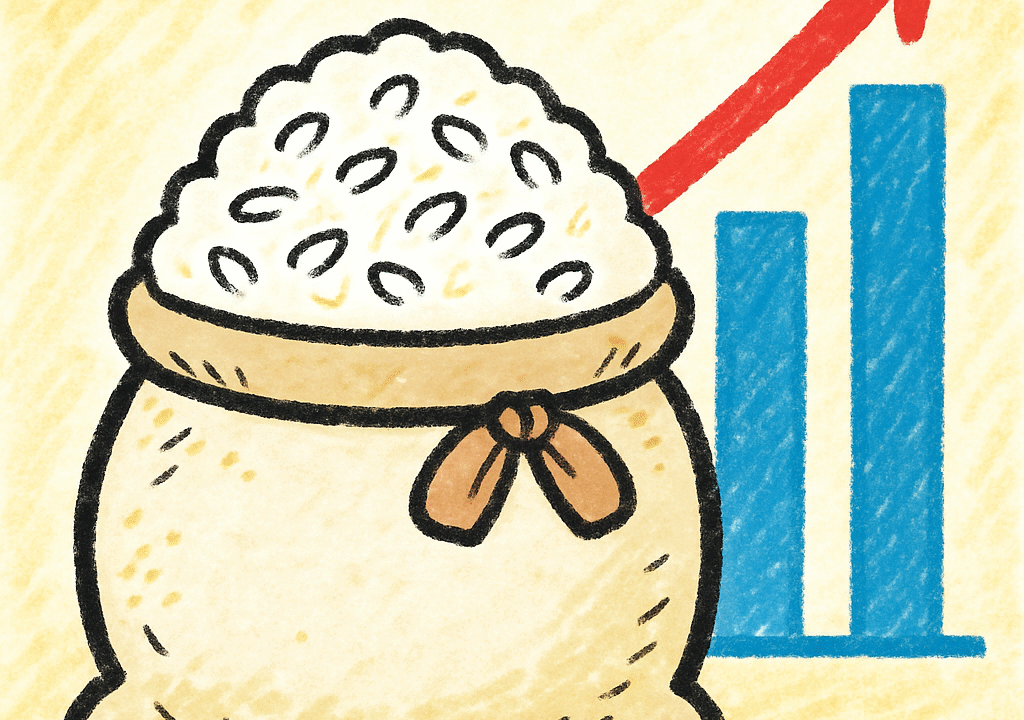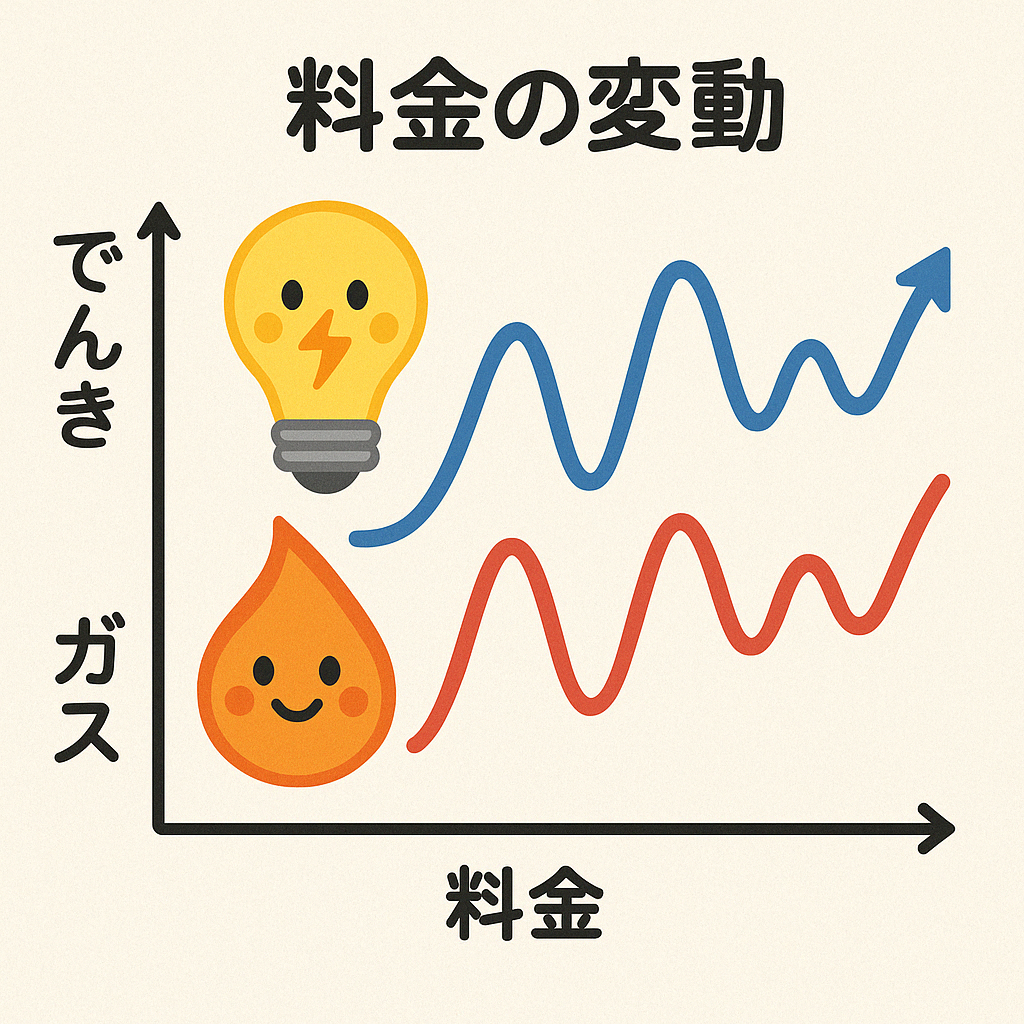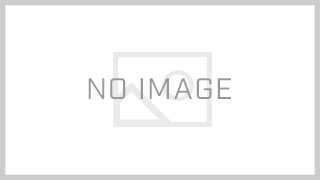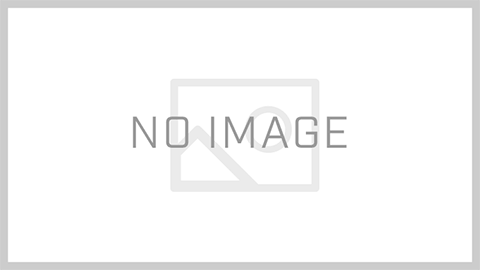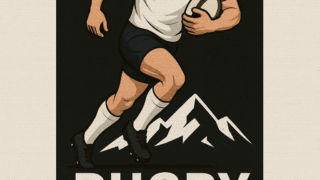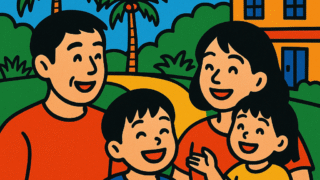最近、スーパーに行くと「米の値段が高くなった」と感じる人が増えています。
2025年現在、5kgあたりの米価格は4,200円前後と、前年の約2倍にまで跳ね上がりました。
この背景には、日本の「備蓄米制度」も深く関わっています。
備蓄米とは?
備蓄米とは、自然災害や不作などの緊急事態に備えて、日本政府が保有している米のことです。
1993年の「平成の米騒動」を受け、1995年に本格的な備蓄制度がスタートしました。
国は常に約100万トンの米を備蓄しており、万が一の際には市場に放出して価格や供給を安定させる役割を持っています。
また、5年を目安に古くなった米は入れ替えられ、飼料や福祉用途にも活用されています。
なぜ今、米が高騰しているのか?
主な理由は、2023年の異常気象による生産量と品質の低下です。
記録的猛暑で登熟が悪くなり、白米として使える量が大幅に減少しました。
加えて、外食需要や訪日外国人の急増による消費増、さらに災害警戒による買いだめも重なり、供給不足に拍車をかけています。
備蓄米の放出が始まった
この異常事態に対応するため、政府は2025年2月から段階的に備蓄米の市場放出を開始。
約21万トンの米を供給し、価格安定を図ろうとしています。
しかし、流通の混乱や買い占めの動きも見られ、すぐに状況が改善するかは不透明です。
まとめ
「備蓄米」は、国民の食の安全を守るための重要な仕組みです。
しかし、異常気象や農業構造の問題が重なった現在、米不足と価格高騰は一朝一夕には解決できない状況にあります。
今後も、備蓄米の適切な運用と、日本の農業支援のあり方に注目が集まっています。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。